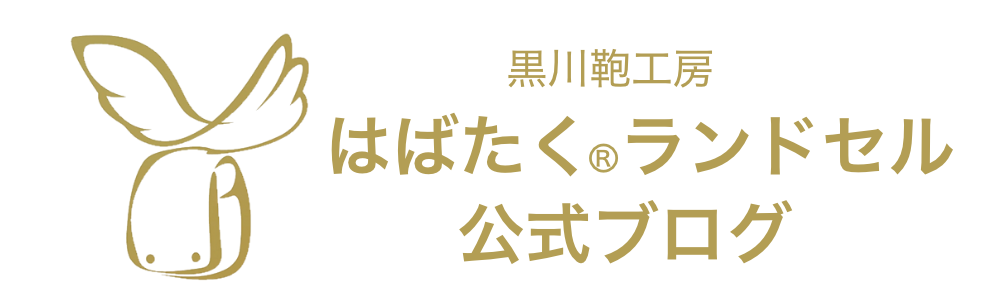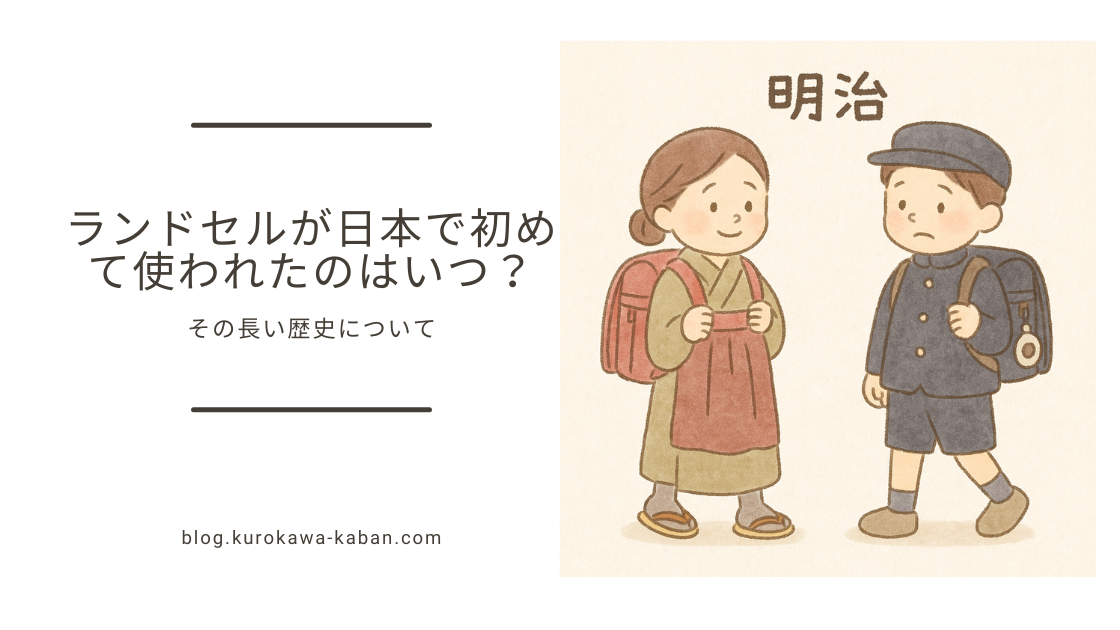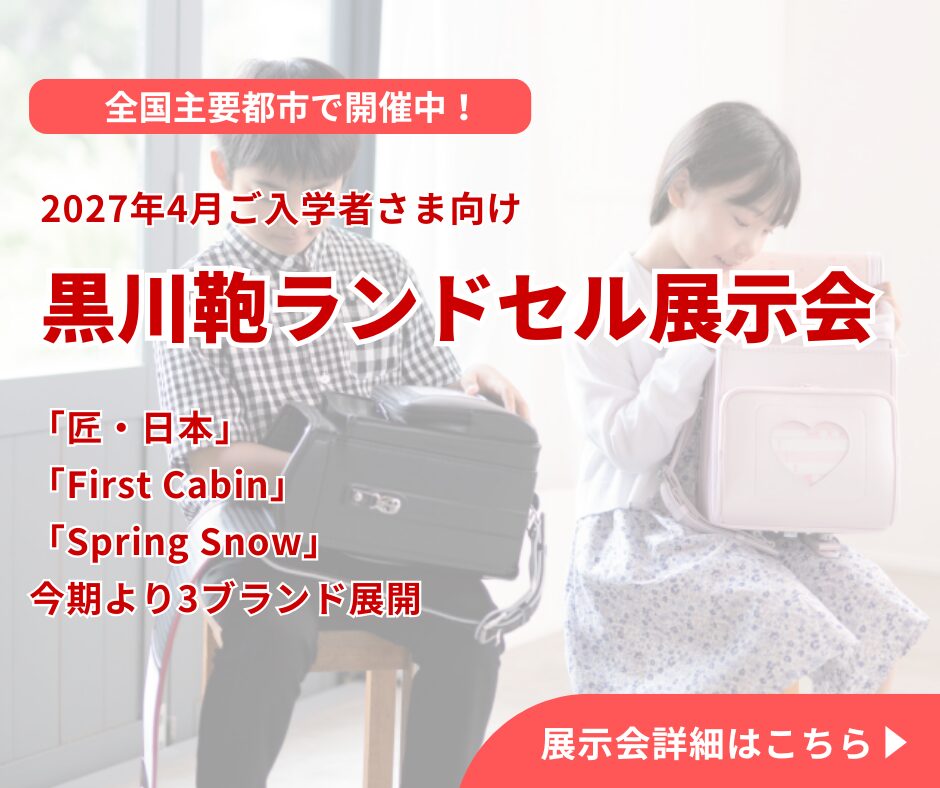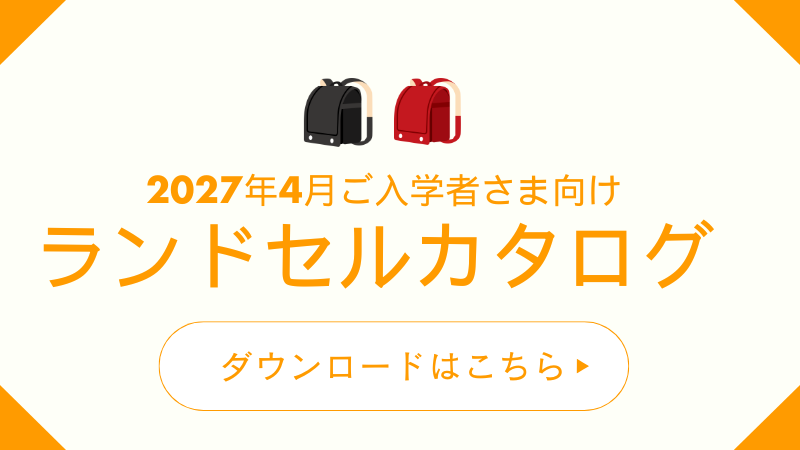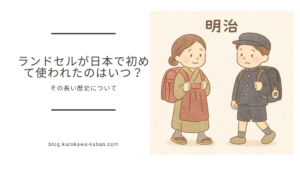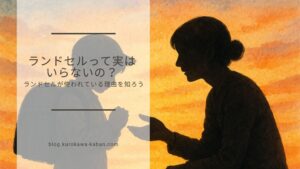ランドセルは、今やお子さまが小学校に入学する際に欠かせない存在ですよね。
色とりどりのデザインが増えた昨今では「どのランドセルにしよう?」と、ご家族の皆さまが一生懸命迷う姿も見られます。
ところで、このランドセル文化はいつ頃から始まったものかご存じでしょうか。
実は明治時代に生まれ、長い年月を経て現在のように定着しています。
今回は、ランドセルが日本で使われ始めた時期や、その背景、そして、歴史を通して培われた「学習院型ランドセル」の魅力について探ってみたいと思います。
さらに、コードバン、牛革、クラリーノ®Fといった現代のランドセル素材とも関係づけてお話しするので、ぜひ最後までお読みくださいね。
 黒川鞄スタッフ
黒川鞄スタッフ歴史を知ると、ランドセル選びもぐっと深みが増しますよ!
ランドセルが日本に初めて登場した背景


日本にランドセルが定着する以前は、いったいどのように学校へ通っていたのでしょうか。
ランドセルの歴史をひもとくには、まず当時の通学環境や教育制度の変革に注目する必要があります。
西洋からの新しい制度が取り入れられるなかで、日本の鞄文化もまた大きく変わっていったのです。
ランドセル導入前の日本の通学鞄
もともと江戸時代後期から明治初期にかけて、子どもたちが通学するときは、風呂敷や布製の袋などで教科書を持ち運ぶことが主流でした。
武家の子弟であれば、専用の書物入れや木製の箱を使うこともあったようですが、一般庶民では“背負う鞄”という概念自体が浸透していなかったのです。
教科書といっても今ほど分量は多くなく、ちょっとした手荷物程度。
それを風呂敷で包み、手提げのようにして運んでいたのが通常でした。
明治時代における教育改革と通学形態の変化
明治時代に入ると、欧米諸国をお手本とした学校制度の整備が進められ、全国的に就学率を高めようという動きが活発化しました。
政府は富国強兵と文明開化を目指し、多くの子どもたちに教育を受けさせる方針を打ち立てたのです。
その結果、学校の数や通学する児童数が増え、従来の風呂敷や箱などでは教科書が運びにくいという声が上がるようになりました。
そこで着目したのが、オランダ式の「背嚢(はいのう)」、つまり背負うタイプの鞄を導入する動きでした。
これこそが、後に「ランドセル」と呼ばれる原型だったと言われています。
初めてランドセルを使用した学校


新しい教育制度とともに導入されたランドセルですが、実際にはどの学校が一番最初に使い始めたのでしょうか。
諸説あるものの、有力視されているのが「学習院初等科」での導入です。
明治時代の終わりから大正時代にかけて、皇族や華族のお子さまが通う学習院で、本格的にランドセルが使われるようになっていきました。
学習院初等科でのランドセル導入の経緯
学習院初等科では、欧米式の教育制度を取り入れる流れの一環として、背嚢型の鞄を生徒が背負うことが提案されました。
外国人教師の影響や、近代教育を実践するという学習院の方針も後押しになったと考えられています。
「手が自由になる鞄」の便利さは、当時の学校現場で大きなインパクトをもたらしました。
大正天皇の学習院入学祝いとしてのランドセル献上
さらにランドセル普及のきっかけとして有名なのが、当時の皇太子であった大正天皇が学習院に入学された際に、元首相の伊藤博文からお祝いとして「ランドセル」が献上されたというエピソードです。
これが世間に大きく報じられたことで、ランドセルの存在が一躍注目を集めることになりました。
皇室ゆかりの持ち物というステータス感も相まって、都市部のご家庭を中心にランドセルが広まっていったのです。
初期のランドセルの評価
導入当初は、まだまだ「背負う鞄」への抵抗感があったことも事実です。
手提げや風呂敷が当たり前だった時代に、洋風の鞄を背負う姿は珍しく、“珍奇なもの”として見られた面もありました。
しかし、両手が空く利便性や、きちんとした身だしなみというイメージが好評を博し、徐々に多くの学校に広がっていきました。
ランドセルの名称の由来とその意味


「ランドセル」という名称は、オランダ語の「ransel(ランセル)」が転じたものとされています。
オランダの軍隊などで使われていた背嚢を日本が取り入れ、発音が変化して「ランドセル」と呼ばれるようになりました。
randselとも表記されることがありますが、やがて日本語として定着し、今では誰もが知る名前となったのです。
学習院型ランドセルの誕生とその特徴


学習院型ランドセルは、かぶせ(フタ部分)と本体が伝統的な形状でつながっている、いわゆるオーソドックスなデザインを指します。
まさに学習院で使用されたランドセルに由来するため、この呼び名が定着しました。
特徴は、かぶせにやや丸みを持たせながらも、しっかりとした枠組みと構造で、中身を守る機能性に優れている点です。
現在でも、コードバンや牛革で仕立てた学習院型ランドセルは高級感があり、たとえば黒川鞄工房はばたく®️ランドセル「匠・日本」シリーズのような職人技が光るものも多く存在します。
頑丈さと伝統的な美しさが共存しているため、長く愛されている形状です。
初期の素材と製造技術


初期のランドセルは主に厚手の牛革やゴートスキンなどが使われており、手縫いやリベット留めによって頑丈さを確保していました。
当時は生産量も少なく、すべてが職人の手作業。
非常に高価な品だったため、限られた層のお子さまだけが背負っていたと言われています。
現在のようにコードバンをはじめとする希少な革を使ったモデル(例:コードバン 艶あり・学習院型など)も高級品として認知されていますが、当時のランドセルは、まさに「憧れの鞄」という存在だったのです。
ランドセルの歴史的意義と未来への展望


ランドセルは、明治時代から大正・昭和と続く日本の教育の移り変わりを象徴するアイテムであり、日本文化と深く結びついています。
海外には類似のスクールバッグがありますが、「6年間ずっと同じ鞄を使う」という習慣は日本独特のものです。
こうした文化は、教育における「継続性」や「責任感」を育む意味でも大切にされています。
日本独自のランドセル文化の重要性
ランドセル文化は、単なる通学具にとどまらず、ご家族の皆さまやお子さまにとって「人生の節目」の象徴でもあると感じます。
入学式にランドセルを背負った姿は、多くの方にとって忘れられない思い出ではないでしょうか。
最近では、黒川鞄工房はばたく®️ランドセル「匠・日本」シリーズのように日本の伝統技術を詰め込んだランドセルや、コードバン・牛革・クラリーノ®Fなど多彩な素材が選ばれる時代になりました。
今後も、職人技と新素材の融合により、新たなランドセル文化が生まれ続けることでしょう。



伝統と革新の両方が息づくランドセル文化。私たちもその一端を担えることを誇りに思います。
よくある質問(FAQ)
ランドセルはいつから日本で使われ始めたの?
明治時代に、欧米式の教育制度が導入されたことをきっかけに、オランダ語の「ransel(ランセル)」が転じたランドセルが使われ始めました。
学習院での導入を通して広く知られるようになり、大正天皇の入学祝いに献上されたことでさらに注目を集めます。
初めてランドセルを背負った人たちはどのような反応を示したの?
当初は、風呂敷や手提げ袋が一般的だったため、「背負う鞄」という西洋風スタイルに戸惑いや珍しさを覚える声もあったようです。
しかし、両手が自由になる便利さや、教科書を衝撃から守れる頑丈さが評価され、徐々に各地へ普及していきました。
現在のランドセルと初期のランドセルの違いは?
一番の違いは素材と製造技術です。
初期は厚手の牛革やゴートスキンを手縫いで仕立てる高価なものでしたが、現代では職人の技を活かした黒川鞄工房はばたく®️ランドセル「匠・日本」シリーズやコードバン、牛革などの本革ランドセルがある一方、クラリーノ®Fのような軽量で水に強い人工皮革も普及し、ご家族の皆さまのライフスタイルに合わせて選べる時代となりました。
まとめ


日本でランドセルが初めて使われ始めたのは、明治時代にさかのぼります。
西洋の教育制度の導入や学習院での採用、そして大正天皇への献上などを経て、一気に広まっていきました。
オランダ語由来の「ransel」が転じたランドセルは、今ではお子さまの小学校生活の必需品として欠かせない存在となっています。
昔は牛革やゴートスキンなどを手縫いで仕立てた貴重品でしたが、現在は伝統技術を大切にするブランドから、コードバンをはじめとした高級素材、さらには人工皮革のクラリーノ®Fなど、多彩な選択肢がそろうようになりました。
学習院型の王道スタイルに加え、キューブ型など現代的なデザインも登場し、機能面でも進化を遂げています。
大切なお子さまが6年間をともにするランドセルには、その背景に日本の教育や文化の歴史がぎっしり詰まっています。
ランドセル選びは、ご家族の皆さまにとって特別な時間。
ぜひ今回の歴史を知っていただいたうえで、素材やデザインをじっくりご検討ください。
ランドセルは、未来へ向かうお子さまを支える大切なパートナーであり、同時に日本が育んできた誇り高い文化の一端でもあるのです。



こうした歴史を知ることで、ランドセルにもっと愛着が湧いていただけたら嬉しいです!